未来の道具
朝晩はだいぶ涼しくなり、過ごしやすい日が増えてきましたね。虫の音に秋の深まりを感じる今日この頃、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
「読書の秋」「スポーツの秋」「食欲の秋」など、秋は色々なことに挑戦したくなる季節です。最近では、これに「学びの秋」を加えて、新しい技術に触れてみるのも面白いかもしれません。
さて、みなさんは最近ニュースやインターネットで「生成AI」という言葉を耳にしませんか? 少し前までは専門家が使う難しい言葉だったかもしれませんが、今では私たちの身近なところで使われるようになってきました。
では、この「生成AI」とは一体何なのでしょうか。そして、どうして文章を作ったり、絵を描いたりできるのでしょうか。 その仕組みをかみ砕いて言うと、「たくさんの情報(データ)を読んで、その中にあるパターンやルールを学習し、次に来るものを予測する」というものです。
なんだか難しく聞こえますか? 例えば、天気予報が過去の膨大な気象データから未来の天気を予測するように、生成AIもたくさんの文章や画像を学習することで、「この言葉の後には、こういう言葉が来やすい」「こういう指示なら、こんな絵が好まれやすい」といった法則性を見つけ出し、新しい文章や画像をまるで人間が考えたかのように作り出しているのです。理科の知識が、未来を予測し備えるために役立つのと少し似ていますね。
これから受験勉強が本格化する中学3年生の皆さんにとっては、この生成AIが心強い学習パートナーになるかもしれません。 例えば、分からない問題の解き方のヒントをもらったり、英作文の練習相手になってもらったり…。便利な使い方がたくさんありそうです。
しかし、便利な道具には注意も必要です。AIが教えてくれる情報が、いつも100%正しいとは限りません。また、AIに頼りすぎて自分の頭で考えることをやめてしまうと、本当に大切な思考力は身につきません。 それは、どんな参考書や学習塾を利用する時でも同じことが言えますよね。大切なのは、道具を上手に「使いこなし」、最終的には自分の力で答えにたどり着くことです。
新しい技術と上手に付き合いながら、自分の力を最大限に伸ばしていってください。皆さんの挑戦を応援しています。
…さて、実は今日のこのブログ記事、私(筆者)が書いたものではありません。
「過去のブログの雰囲気を真似して、生成AIをテーマにしたブログを書いて」と、私自身がAIにお願いして、作成してもらったものなのです。 驚きましたか? 指示の仕方によっては、こんなに自然な文章を作ってくれるのです。
便利な未来の道具、皆さんもぜひ、その可能性と賢い付き合い方を考えてみてくださいね。
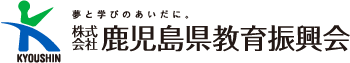


 PAGE TOP
PAGE TOP